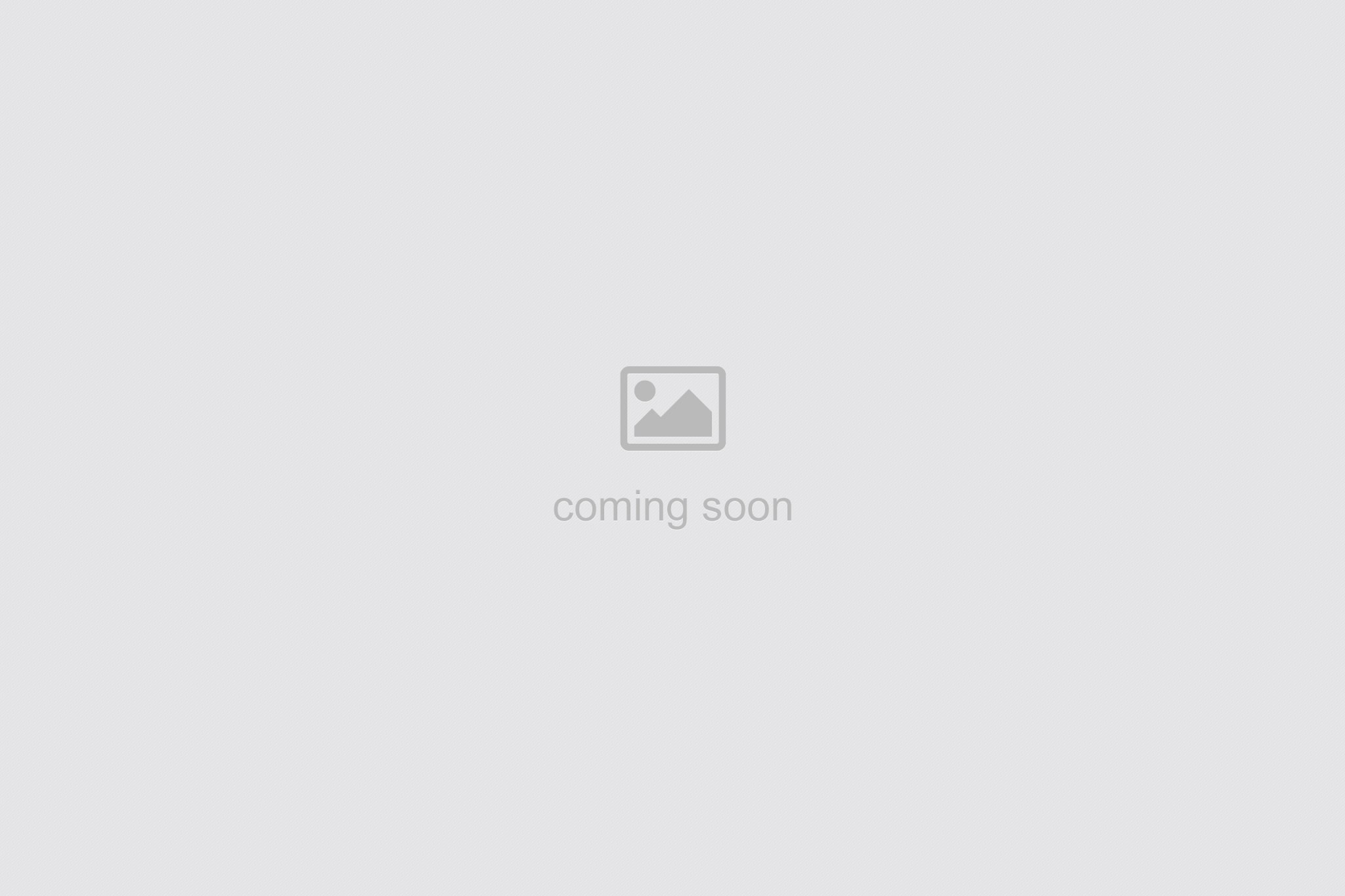『今徒然』 ~住職のひとこと~
今徒然 記事 一覧
第39回 ~小説『嘔吐』~
2023-10-01
実存主義の“聖典”といわれるジャン=ポール・サルトルの小説『嘔吐』 La Nauséeは、率直に言って退屈でつまらない小説である。カフカの影響があると評されるが、私には、むしろ戦後のフランス小説界で一時ブームとなったヌーヴォー・ロマンとか、アンチ・ロマンとかの先駆けと見えなくもない。ストーリーに情感や起伏が乏しく、ブーヴィル Bouville(泥の町)という港町に住み着いた30歳の研究者、ロカンタンが図書館や公園に通い、港町の雑踏に紛れて日常生活を送りながら、自身の内部で意識と存在そのものの葛藤と乖離に悩み苦しむ。救いようのない意識の病の話だ。
『嘔吐』は、ある意味で実験小説である。モチーフは、この小説から数年後世に出ることになる『存在と無一現象学的存在論の試み』 L,Être et le néant: Essay ďontologe phénoménoloquique に解き明かされている。《対自存在》と《即自存在》の相剋の構図がそのまま小説『嘔吐』に落とし込まれている。これに“心身症”の調味料をふりかけて、レアリティを醸し出すという手筈だ。『嘔吐』のクライマックスで主人公ロカンタンは、マロニエの木の根っこを凝視して嘔吐の発作を催す。意識によって暴かれた無意識でのっぺらぼうのむくつけき存在そのものの根っこの露出である。
後にも先にも、これだけが小説のテーマである。意識を向けることによって事物は存在する。意識の《志向性》というのは、フッサール以来の現象学の述語だが、サルトルもこれを継承している。しかも、宿命的な意識の病として継承している。夕闇が落ちかかった窓辺に佇んで、主人公が嘔吐感を覚える場面。これなどは、口の中に舌があるのを意識すれば、誰でも気持ち悪くなって嘔吐しそうになる一種の心身症と区別がつかない。《対自》としての人間存在にとって、《即自》はグロテスクな嫌悪感の対象でしかない存在の固まりであって、この両者は永遠に和解することはない。
『存在と無』は、一貫して厳密な理論性を以て書かれている。これまでに成された実在哲学のように、情念とか感情がはみ出て、理論的整合性が欠けて逆説に陥ることがない。小説『嘔吐』の主たるテーマ《対自》と《即自》との執拗な絡み合いが、実存主義の真相である。人間的現実とは《無化作用》つまり「あるところのもの」を否定して、不断に《脱自》し、未来に向かって《投企》し、世界との関わりにアンガジュマンすることだ。実存的主体性の選択はいつでも何処でも自由である。むしろ「人間は自由の刑に処せられている」「無益な受難である」ことを引き受けねばならない。
※エピローグ:大学院の頃、サルトルについて論文を書いたが、その中でサルトルに批判的なジョルジュ・プーレの一文を引用した。論文の審査評価をされる教官の中に、『存在と無』を翻訳された松浪信三郎先生がおられた。先生は穏やかにむしろ愉快そうな表情でこう言われた。「G.プーレは、サルトルを誤解している。したがって、君の論文は誤解に基づいて書かれている。」……ほぼ半世紀前の話になる。
令和5年 10月1日