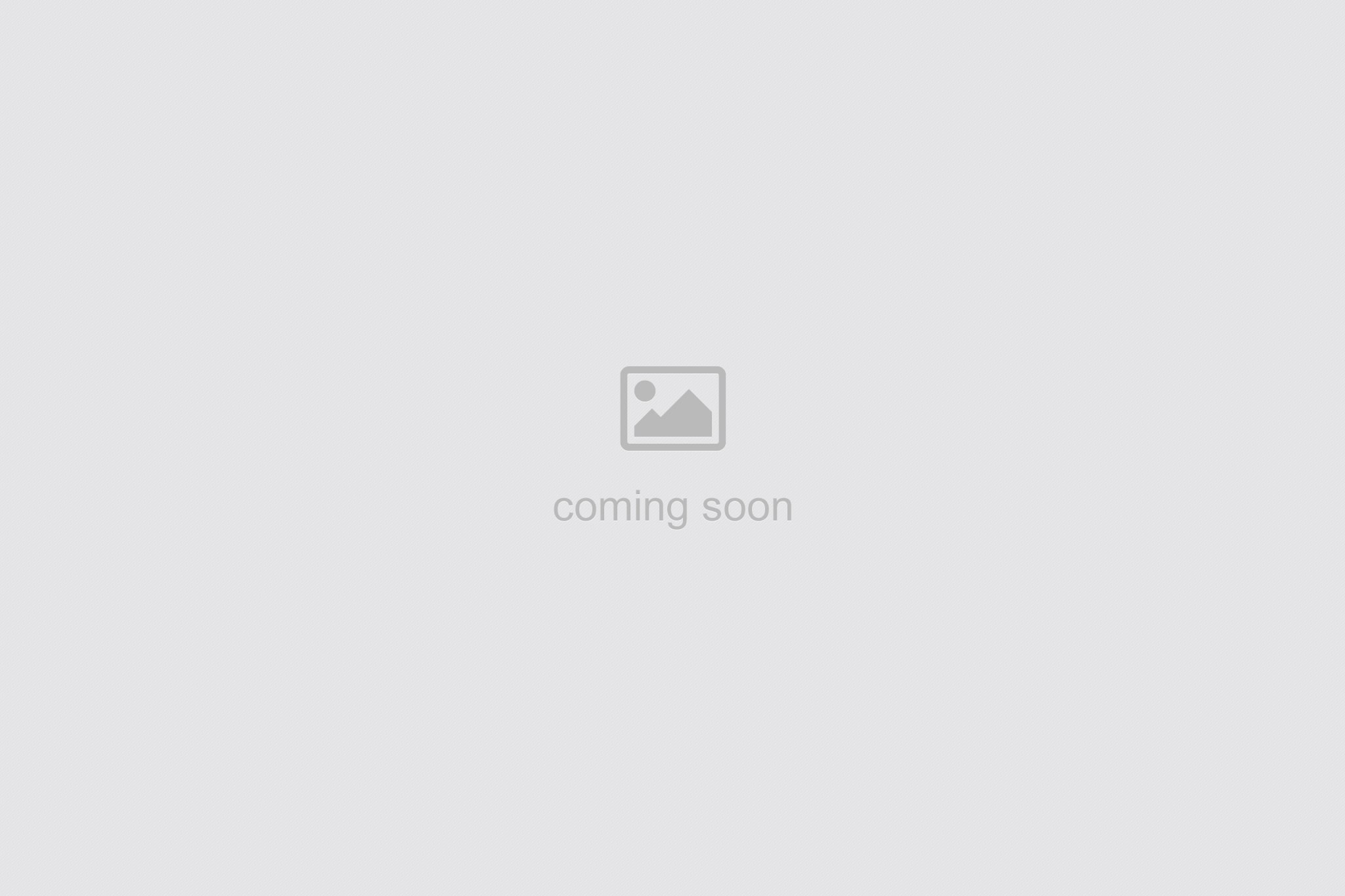『今徒然』 ~住職のひとこと~
今徒然 記事 一覧
第43回 ~絶望のリテラシー~
2024-02-01
「絶望して死ぬことさえできない絶望」とキルケゴールは言った。「あらゆるものを表現し、そのことごとくに絶望しきって死んでいきたい」とアンドレ・ジッドは嘆いた。ドストエフスキーの『罪と罰』の主人公ラスコリニコフは、ぬかるみで泥塗れになった絶望を抱えてのたうちまわる。人生は、あたかも絶望のメモリー。この絶望がいつどこで始まり、またいつ終止符をうつのか、誰も知らない。絶望は、『死に至る病』なのか、或いは、人生そのものの別称とでもいうべきなのか。そもそも絶望についてかくも饒舌に語ろうとする自分自身は、既に東西南北の去来なき孤老に過ぎない。
仏教でいう《生老病死》は、苦と絶望のプロセスである。どう文言を修飾しても、これが、幸せと好運へのステップであるとは言い難い。大半の人々にとって、人生は苦と不運とで出来ている。たまたま運に恵まれ、幸福な状態にあっても、それがいつ覆されるか、不安と恐怖につき纏われる。六道講式に曰く「世間は車の輪の如し……人も亦車の輪の如し。或いは上り、或いは下る云々」。此の世の無常も肯定的、能動的に観ずれば、“下克上”にでもなるのだろうか。だが、下が上を喰らい、転倒上下する砌の苦と恐怖は、やはり無明の闇夜の底知れぬ絶望の淵に通底している。
絶望のどん底からしか、希望の光は見えない。『リア王』にはこんな台詞がある。「不運ばんざい! 運の女神に見放され、この世の最低の境遇に落ちたなら、あとは残るのは希望だけ、不安の種もなにもない!」 何だか自暴自棄のつよがりにも聞えるが、なるほどそう言われれば、絶望のどん底も居心地が悪くはない。「おいらは阿呆だが、あんたはなんでもない。」リア王の狂気につき纏う道化師の戯れ言は、真実を穿っている。なんでもない。何者でもない“nothing”が、唯一の希望であり、救いなのかもしれない。この“nothing”は、「本来無一物」の意と必ずしも無縁ではない。
「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」と親鸞上人は説いたが、善人を差しおいて、悪人にこそ往生の根機があるとは、一見筋が通らぬ逆説にみえる。だが、濁った泥沼に咲く白蓮がひときわ美しいように、極悪に穢れた煩悩具足の凡夫こそ、阿弥陀仏の本願に適うべしと、親鸞は考えた。そして、衆生としての人間を根源的な悪と捉えた。ここには、人間の本性への深い洞察と絶望がある。「いずれの行も及びがたき身なれば、」自分自身もまた一つの絶望に過ぎない。つまり、南無阿弥陀仏の外、何もたない無一物、リテラシーとしてはnothingということになるのだろうか。
令和6年 2月1日