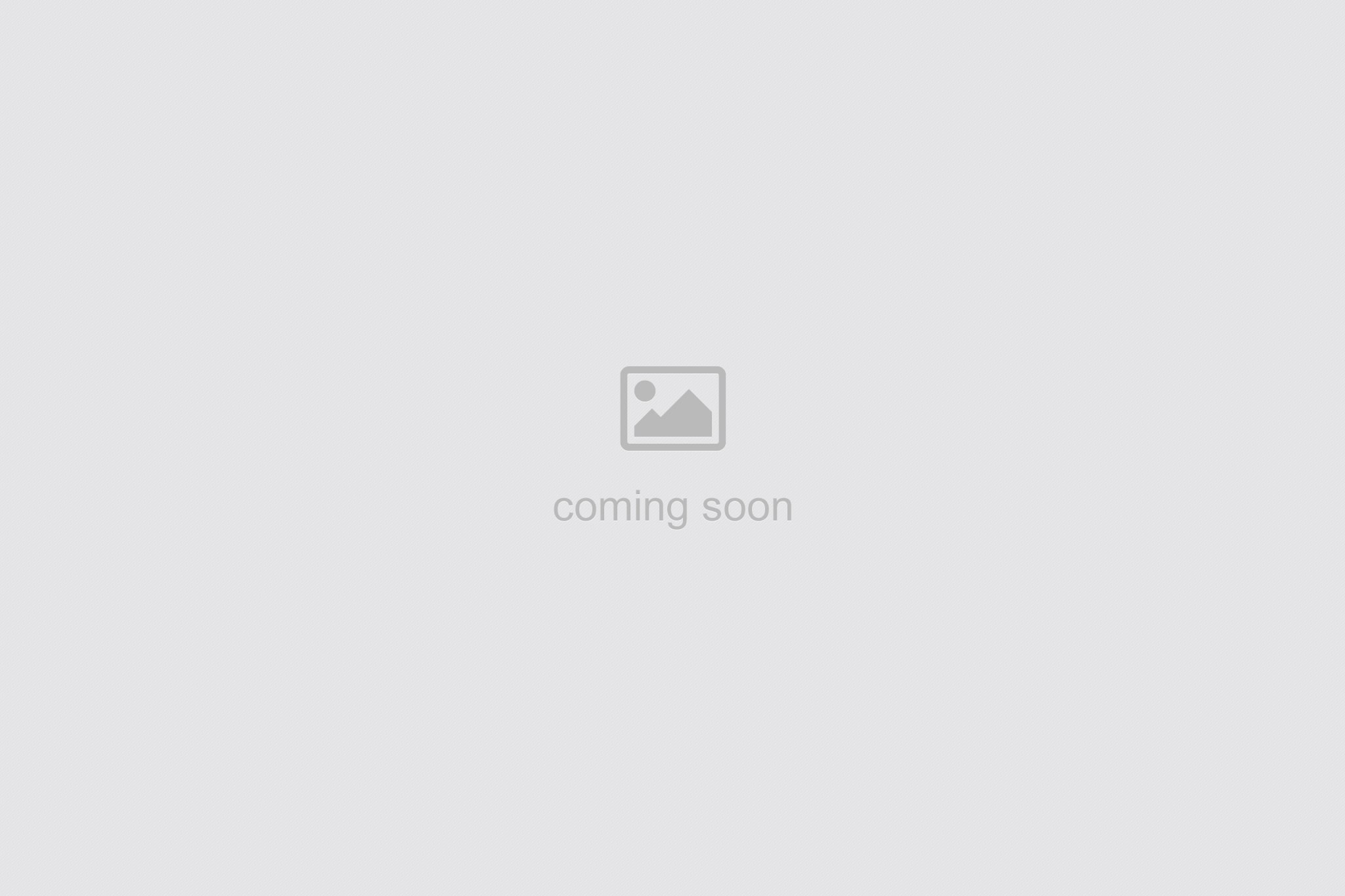『今徒然』 ~住職のひとこと~
今徒然 記事 一覧
第45回 ~思想の履歴~
2024-04-01
浅田彰著の『構造と力』を読んだのは、久しい以前のことだが、読みながら、私は、学生時代に或る友人に揶揄された言葉を思い出した──「君は、思想的に苛められたキリーロフだ」 キリーロフとは、ドストエフスキーの『悪霊』の作中人物で、神と対決し、神がいなければ自分が神だ、窮極にまで、自分の意思を貫くことで、自ら生命を断って、神の存在に挑むという、いわば一種の“パラノイア”なのだが、これが単なる偏執狂と異なるのは、相手が神だということである。命懸けの確信と全人類の憎悪をこめて神と共に奈落に沈む必殺技は、とても私の想いつくところではない。
同様に「神は死んだ」と自ら“神の殺戮者”と自称し、ツアラツゥストラの登攀を演出した十九世紀のドイツの哲学者ニーチェは、従来のキリスト教の価値観で築かれた既成の世界を根底から覆そうと企てた。「人間は動物と超人の間に張り渡された一本の綱である──深淵の上にかかる綱である。渡って進むのも危うく、立ち止まるのも危うく、後ろを振り返るのも危うい」何というスリリングで戦慄的な限界状況であろう。彼は「人間は乗り超えねばならぬ或るものである」と定義し、危険と戯れる飽くなき超人として、深淵に張り渡された綱の上でアクロバットも演じかねない。
神と個人の対決のテーマは、同時代のデンマークの哲学者ゼーレン・キルケゴールの『死に至る病』にも忍び込んでいる。「人間は出来るだけ遠く神から離れていなければならない。神に最も近くに迫ることができるのは、神から最も遠く離れている場合である。」明らかに、逆説的表現だが、神に迫ろうとして挫折し、神との無限の断絶を感じた砌こそ、信仰的モチベーションを高める契機とされる。神と個人の間に絶対的な距離があってこそ、神に最も近いところにあって、キリスト者として、不断に信仰をアップデートすることができる。キリーロフ/ニーチェと裏返しの論理である。
実存哲学といわれるものの最初のテーマは、神と個人の関係をいかして適正化し得るか、さもなければ、神といかにして手を切るか、ということにあったように思われる。実存哲学は、サルトル以後、現象学による方法を駆使して、人間を意識存在として探究した。神と人間の関係は既に清算された。清算されたことが前提で、ポスト・モダンやその後の思想的展開も図られた。だが、ロゴスとかディスクールとか差異などのポスト・モダンの語彙のなかに、既に清算したはずの神のにおいは紛れ込んでいないか。少なくとも、浅田彰著『構造と力』には、神という語は一度も出てこない。
令和6年 4月1日