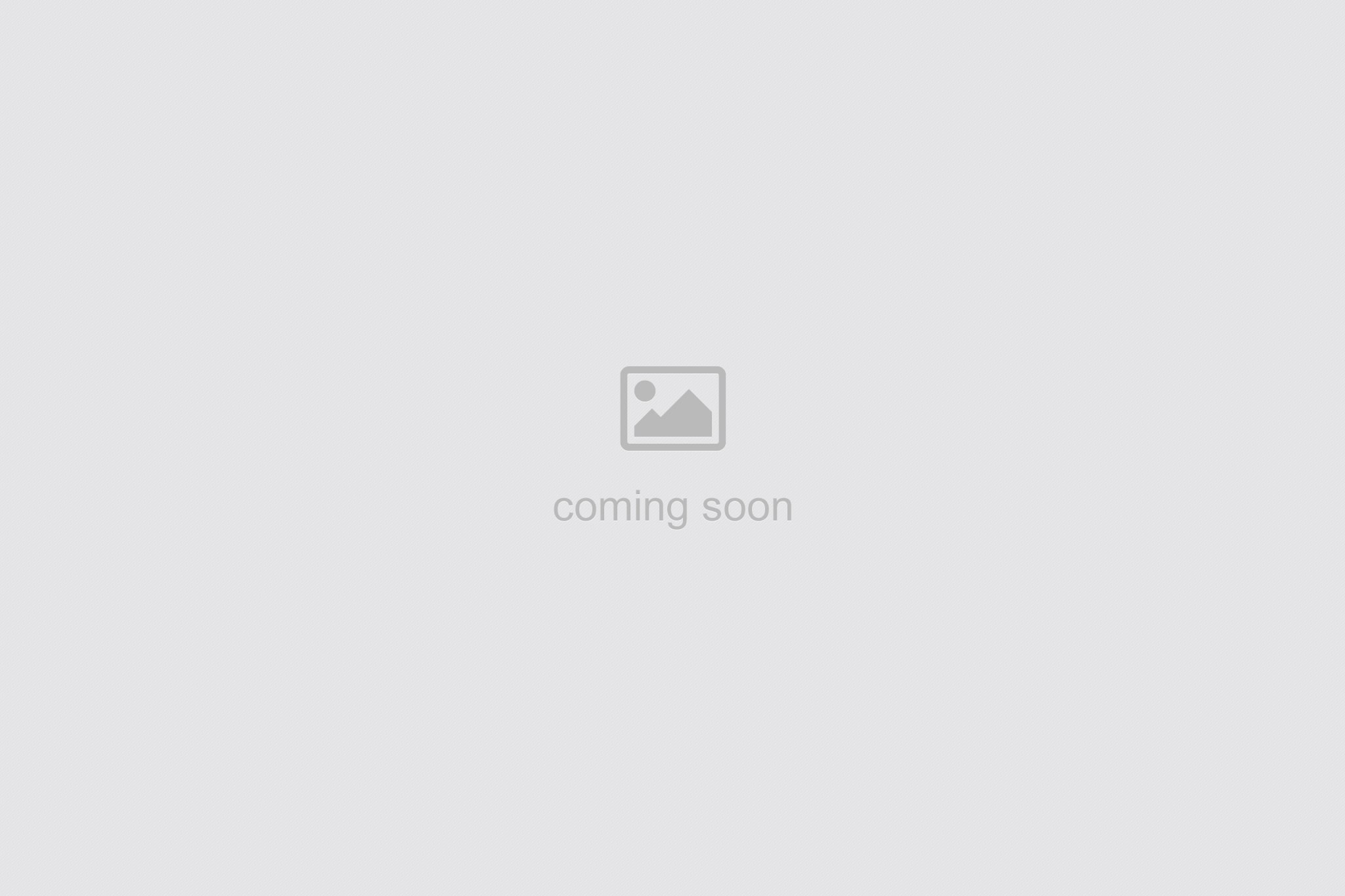『今徒然』 ~住職のひとこと~
今徒然 記事 一覧
第46回 ~批評家・小林秀雄~
2024-05-01
昭和の文壇で、鋭い洞察力と自在な文章で知られた批評家・小林秀雄は、著書『様々なる意匠』に次のような一文を遺している。「批評とは竟に己れの夢を懐疑的に語ることではないのか」若い頃読みとばした言葉が歳を経て、意味そのものや筆者の意図することろが変わって来たように思えるのは、私自身が変わったということだろうか、或いは、ただの錯誤だろうか。批評についてのこの厳しい問いかけは、他の曖昧な定義や解釈を拒んで、我々の前に立ちはだかる。当然のことながら読者としての些かの妥協も安易も排され、結果我々の感想それ自体も行き場を失うことになる。
批評とは、他人の作品を素材にして好き勝手に切り刻んで料理しているようなものだ、と云った知人がいたが、冒頭に掲げた小林秀雄の観点から申せば、批評の対象は、他者でありその作品である以前に、まず自己であり「己の夢」である。前後の文脈を辿れば、この己の夢は自意識とか、自覚とかいう語に変換することもできる。「三界唯一心 心外無別法」の境地に通じるものがある。即ち、心=自意識の外に拠り所はない。己の自意識によって、作品・作者の宿命的声音を聴く時、夢の陰翳が晴れて「私の心が私の言葉を語り始める」そこに批評の可能性があると彼は断言する。
作品が作者の手を離れたときから、作品は一人立ちして歩き始め、作者は置き去りにされる。作者の人生の現実と作品の価値は何の関係もない、という論調を我々はしばしば肯定して聴き入れた。果たして、そうだろうか。ここでも小林秀雄は、逆転の発想を遺憾なく披瀝している。作品は、作者にとって、単なる里程標に過ぎぬ。彼に重要なのは歩くことであって、その里程標を見る人々が、何を感じ何処に向かうかは、彼の與り知らぬことである。歩くと言えば、アフリカで隊商を率いて、壊死しかけた脚を引き摺り跛行し、地を這うように彷徨ったランボーの姿を想起せずにはいられない。
この「途轍もない通行者」の俘囚となった若き日の小林にとって、『地獄の季節』は詩人アルチュール・ランボーが憑依した詩的言語、それ以上のものだったのかもしれない。彼が出逢ったもう一人の天才ドストエフスキーについて、彼は『ドストエフスキィの生活』という“観察記録”を書いている。シベリア流刑の悲惨と絶望、神経の昂奮と衰弱、奇跡的な『罪と罰』の成功、妻に跪いて許しを乞う賭博者の哀れな素顔、具に描かれた作家の生活は見るに堪えない。あたかも、小林は、後作『白知』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』などの“里程標”の文学的巡礼者であるかのようだ。
令和6年 5月1日